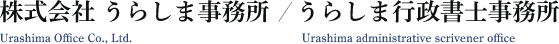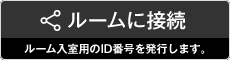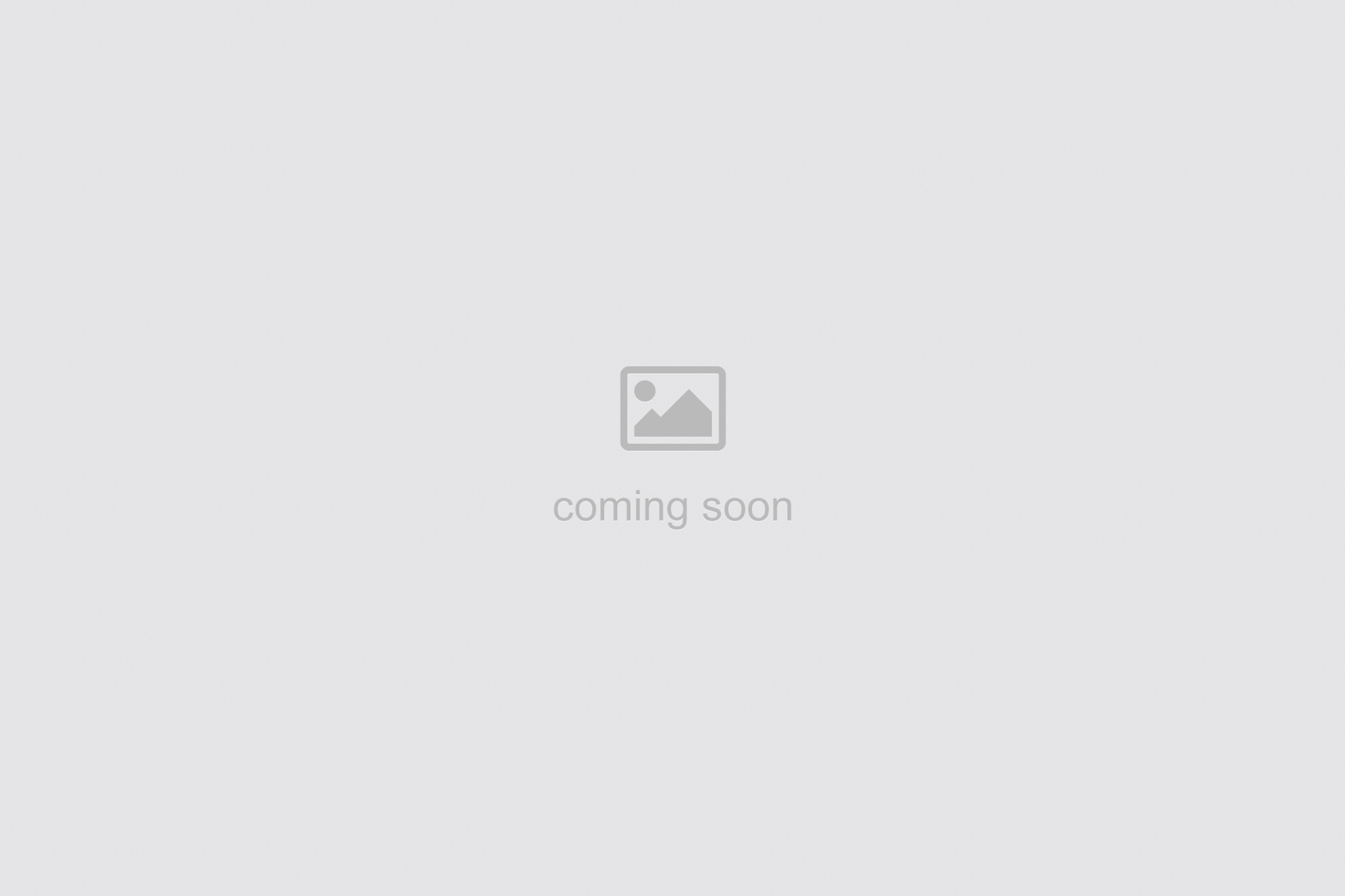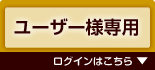福祉用具貸与申請基準について大まかにみてみましょう。
福祉用具貸与とは→こちら
 人員に関する基準
人員に関する基準1:福祉用具専門相談員が常勤で2名以上必要です。
※資格必須:介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、ホームヘルパー2級以上の資格保持者、福祉用具専門相談員指定講習を受講し所定の課程を修了した者
※平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員の要件が改正されます。
養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)は要件から外れ、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)および福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されます。経過措置期間が1年設けられているので、養成研修修了者で現在福祉用具専門相談員として従事されている方は、平成28年3月31日までに福祉用具専門相談員指定講習を修了するか、国家資格を保有する必要があります。
2:常勤の管理者がいなければいけません。
 設備に関する基準
設備に関する基準1:福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び機材、事業の運営を行う為に必要な広さを有する事務所が必要です。
2:利用申し込みの受付・相談等に対応する適切なスペースを確保しなければいけません。
3:指定福祉用具貸与に必要な設備及び備品等を確保しなければいけません。
4:既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほか、パーテーションの設置などで保管を明確に区分する措置が講じられていなければいけません。
 運営に関する基準
運営に関する基準1:利用料等の受領
2:指定福祉用具貸与の基本取扱方針
3:指定福祉用具貸与の具体的取扱方針及び福祉用具貸与計画の作成
4:運営規程
5:適切な研修の機会の確保
6:衛生管理等
7:記録の整備

福祉用具貸与事業所の指定申請に必要な書類
指定申請に当たっては、人員・設備・運営等に関する基準をご確認頂き、下記の1~14の書類及び『介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出』書類が必要となります。
但し、これ以外の書類が必要となる場合もあります。(ご紹介は宮城県での申請の場合です。)
指定を受けようとする申請法人及び事業所の概要等を記載する書類です。
指定を受けようとする事業所の概要(管理者名、従業者数、営業日等)を記載する書類です。
3:申請者の定款、寄付行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等
申請者が法人であることを確認するための書類です。
原本証明した定款等の写しと登記事項証明書(原本)を添付しなければいけません。
※定款等における法人の事業目的の中で介護サービス事業を行うことを明記する必要があります。
例)『介護保険法に基づく居宅サービス事業』『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』等
従業員全員(管理者含む)の勤務体制(4醜聞の予定)を記載しなければいけません。
5:従業者の資格証写し(福祉用具専門相談員)
4の『勤務表』に記載した従業者のうち、福祉用具専門相談員である者の資格証の写しを添付しなければいけません。
6:従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
4の『勤務表』に記載した従業者が、事業所に配置される事実を確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書等)の写しを添付しなければいけません。
事業所管理者の経歴について記載しなければいけません。
既存の図面等(用途・面積を記載)があれば、参考様式に代えて提出することもできます。
サービス提供のために必要な福祉用具の保管・消毒のために必要な設備等について記載しなければいけません。
10:福祉用具の保管・消毒の方法
福祉用具の保管・消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該委託事業者の名称・所在地及び委託契約の内容等が分かる書類(委託契約書等)を添付しなければいけません。
11:運営規定
運営に関する基準で求められている必要事項について定めた規定を添付しなければいけません。
運営に関する基準で定められている必要事項(苦情の受付窓口・苦情処理体制・手順等)を記載しなければいけません。
13:資産の状況
介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合に、その賠償資力を有していることを確認するための書類を提出しなければいけません。
(具体的書類)
・損害保険証書の写し
・資産の目録
・直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
申請者、申請者の役員等が介護保険法に定められた欠格事由に該当しない旨及び暴力団員 等に該当しない旨を誓約する書類です。
申請法人の役員等について、氏名・住所等を記載しなければいけません。
参考様式につきましては、こちらからもご覧いただけます→ こちら